
松戸市、市川市、宮大工が手掛ける古民家再生・注文住宅の工匠、広報担当です。
皆様こんにちは。
近年の住宅事情の中で「省エネ基準の適合義務化」という言葉は耳にしたり、見かけたりすることがあるかもしれません。
2025年4月より全ての新築で省エネ基準適合が義務化となることに併せて法改正が行われ、木造戸建住宅の建築確認手続きが変わります。
住宅を建築するにあたっては、この法改正に関わらず確認申請書など必要書類を揃えて、審査を受けなければ工事を始めることができない決まりになっています。その中で、2024年現在一般木造住宅のほとんどが該当する「4号建築物」に対しては、確認申請の書類が一部簡略化されています。
2025年4月から施行される法改正後、この「4号建築物」という区分はなくなります。これからマイホームを建てようとしている方、ほとんどの場合がこの新ルールに従って家づくりを進めることになります。わかりやすく解説するので、是非参考にしてください。
-目次-
・そもそも「建築基準法」とは
・4号特例とは
・4号特例ができた背景
・4号特例見直し3つのポイント
・法改正の理由
・法改正がもたらす影響
・まとめ
「建築基準法」とは、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めています。建物の基準を定めることによって、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、安全で幸せな暮らしをつくる助けとなるためのものです。
建物を造る際には、この法律に基づいた様々な規制をパスしている必要があるのです。
2024年現在、建築物は、第1号、第2号、第3号、第4号に分けられています。
その中で今回大きく見直されるのは4号建築物です。
|
4号建築物とは |
つまり、現在建てられている木造住宅のほとんどが4号建築物に分類されており、「4号特例」という法に準ずる審査を受けて造られています。
今回の法改正は「4号特例」見直しということになります。そして、改正後は「第4号」という区分はなくなります。
住宅を建てるにあたって、とても大切な建築基準法ですが、今回の見直しは具体的にどのようなものなのでしょう。
まず、2024年現在の4号特例とは、どのようなものなのでしょう。
一般的な木造住宅のほとんどが該当する4号建築物は、審査省略制度の対象となっています。構造計算書など、確認申請の手続きを一部省略でき、チェックも受けません。
この制度がいわゆる「4号特例」です。これは建築基準法に適合しない建物を造っていいということではありません。建築士が設計したという事を担保に安全な建物であると判断ができるというものです。
なぜ、このような簡略化が行われてきたのでしょうか。
4号特例が導入された1983年、日本は経済成長を経て住宅の着工件数が急増しました。建築確認や審査をする行政の人手が不足し、審査が滞ったり業務過多が問題になりました。それらの問題を緩和するためにできたのが「4号特例」です。このような背景を考えると、今とはだいぶ状況が違いますので見直しも当然の事なのかもしれません。
今回の法改正のポイントはなんでしょう。
①「建築確認・検査」「審査省略制度の対象範囲」が変わる→「4号建築物廃止➡新2号、新3号へ」
②確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要
③2025年4月に施行(2025年4月1日以降着工はこれに該当)

出典:国土交通省
つまり、2階建てなら、延べ面積に関わらず「新2号建築物」になります。更に、平家でも延べ面積が200㎡(約60坪)を超えると同じく「新2号建築物」になります。
※現在の4号特例と同じ扱いになるものは、「平屋」かつ「延べ面積が200㎡以下」の建築物だけになり、「新3号建築物」となります。

出典:国土交通省
これまで4号建築物と扱われていた建築物でも新2号建築物に該当する場合、構造関係の図面などの添付が必要となります。また、省エネ関連の図書も必要になります。
上記を含め、これまで特例として提出が不要だった図面や計算書が、新2号建築物に該当するものは添付が必要となります。
※新2号建築物になった建物であっても、認められた規模の建物において、仕様表で構造安全性を確認できるという合理化も図られています。

出典:国土交通省
2025年4月1日以降に着工の建物はこの法改正の対象となるので、それ以前に申請を提出している場合にも注意が必要です。
2024年現在、申請書が一部簡略化されていた4号建築物のうち、最も一般的な住宅のほとんどが、「新2号建築物」に振り分けられることが分かります。4号建築物の区分を廃止し、新3号、新2号建築物に振り分けたことで、審査省略制度(いわゆる4号特例)の該当範囲を大幅に見直したことになります。よって、多くの住宅が審査省略制度に該当しなくなるということです。2025年4月より新2号建築物になった住宅は、提出不要だった図面、計算書、「構造関連の図書」、新たに加わった「省エネ関連の図書」の提出も必須になります。
4号特例見直しにはどのような意味があるのでしょう。
4号特例見直しの背景は主に3つ。
① 住宅省エネ化の促進
② 断熱材や省エネ設備などによる建物の重量化
③ 倒壊リスクの回避
2050年までのカーボンニュートラルの実現に向け、建築分野では省エネに関する補助金の見直しや住宅ローン減税見直しなど、段階的に様々な形で省エネ住宅への移行が促されてきました。そして、いよいよ2025年4月より多くの住宅に対して省エネ基準適合が義務化するのです。
建築確認申請が今まで通り免除されている状態では、定めた省エネ基準に適合しているのかをチェックをすることができません。最も多く建てられる一般的な木造住宅を一部簡略化制度の対象から外して省エネへ適合義務が果たされているかを確認できる仕組みが必要になったのです。

近年求められている、断熱材や省エネ設備の搭載に伴い、全般的に建物の重量が増加している傾向にあります。重量が増加した分、当然相応の強度が求められます。倒壊のリスクを減らし、安全で適切な設計・施工を約束するためにも、法改正の必要があるというのは当然の流れなのです。

これまで4号特例があったことにより、2階建て以下の木造住宅では確認申請で構造計算などの審査を受けずに建物を建てることができました。もちろん、建築士が設計した建物のほとんどは安全が根拠となる設計がなされていますし、新築に関していえば、ほぼ全ての工務店が何らかの形での安全確認書類を作成しているはずです。しかし、実際にはリフォーム等含め、法をすり抜けてしまった倒壊リスクの高い建築物があることも問題視されています。
建築士のモラルを信頼した制度となっている現在、もっと過去をたどれば大工の「経験と勘」に頼って建てた家もあったと思います。今回の法改正により、一般的な住宅の構造がしっかりとチェックされることになりますので、安心で安全な住まいが確実に手に入るということになります。
法改正によって、私たちにどのような影響があるのか、それが一番きになるところです。
簡単にずばり!
|
・着工までの時間が今まで以上にかかります。 |
申請書の作成に時間がかかるようになり、また審査にも時間がかかる事が予想されます。省エネに対する審査には更なる審査延長もありそうです。書類作成、確認作業など費用も増えることになります。

例えば、新築の流れだと基本設計を終えた段階で確認申請の作成を開始し、並行して実施設計を進めていくという事が可能でした。しかし、法改正後は、確認申請提出の時点では変更のないよう、全ての設計を終えておかなければ必要な図書が揃いません。
確認申請までにすべての必要書類を揃えなければいけないのと、許可が下りるまで目安として1~2ヵ月、ほぼなんの準備もできない待ちの時間になりそうです。新たに追加された省エネ関係の審査にも、更なる時間がかかることや多少の混乱も予想されています。
せっかく注文住宅を考えるなら、たっぷりと時間をかけて理想の住まいを叶えられるように、色々な事情を考慮しながら、時間に余裕をもって家づくりを計画しましょう。
この法改正がもたらす影響は悪い事ばかりではありません。確認申請の厳格化でしっかりと基準を満たすということは、構造、耐震性能、安全性の向上が期待されます。一定の安心な住まいを手に入れることができるのです。そして、もう避けて通れない省エネ、カーボンニュートラルの実現にむけて、地球にも私たち暮らす側にも優しい住宅になっていく事が期待されています。
今回は、4号特例の簡単な仕組み、導入背景、2025年の法改正による4号特例見直しによる変更点、マイホームを考えている方々への影響をまとめました。
弊社、工匠では自然素材たっぷりの木造住宅「結」というセミオーダーの住宅のご提案をさせていただいております。

標準仕様があるので、価格を抑えてご提案ができます。そのなかでも間取りをお客様と一緒に考えることができ、住みやすさ、自分らしさを叶える家にしていただけます。法改正後も合理化が図られている仕様表添付での対応が可能な住宅になりますので、手続きに関するコストを抑えることができ、申請書提出までの時間短縮も可能です。充分に整った設備と建材で考えられた工匠オリジナルの仕様です。お客様の要望にもお応えできるようセミオーダーと位置付けております。たくさんの想いをお聞かせください。
詳しくは→セミオーダー住宅「結」
今回の記事は、新築を中心に書きましたが、この法改正は、大規模修繕やリフォームなどにも大きな影響があるため、次回はそちらについてもまとめておこうと思います。
「建築事業を通してかかわるすべての人に安心・笑顔を提供していく。」を会社理念としている工匠では、今までと変わらず安全で温かな木の家のご提案をさせていただきます。お客様と楽しく願いを叶えていける、注文住宅ならではの家づくりをしたいと思っています。
信頼できる建築士が一緒に間取りを考え想いを描いていきます。木をよく知る大工が一棟一棟丁寧に修復、建築いたします。安心して工匠にご相談ください。
工匠は、千葉県松戸市・市川市を中心に自然素材を活かした古民家再生・注文住宅を手掛けています。
いつまでも丈夫で美しく、愛され続ける住宅をご提供いたします。
家づくりに関するご相談、お悩みなどお気軽にお問合せください。
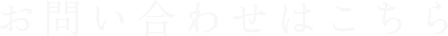

古民家再生を行い、私たちらしい暮らしを叶えたい。

他社で診てもらったら「建て替えた方が」と勧められたが、本当にそうなのか?

予算や間取りなど相談したい。